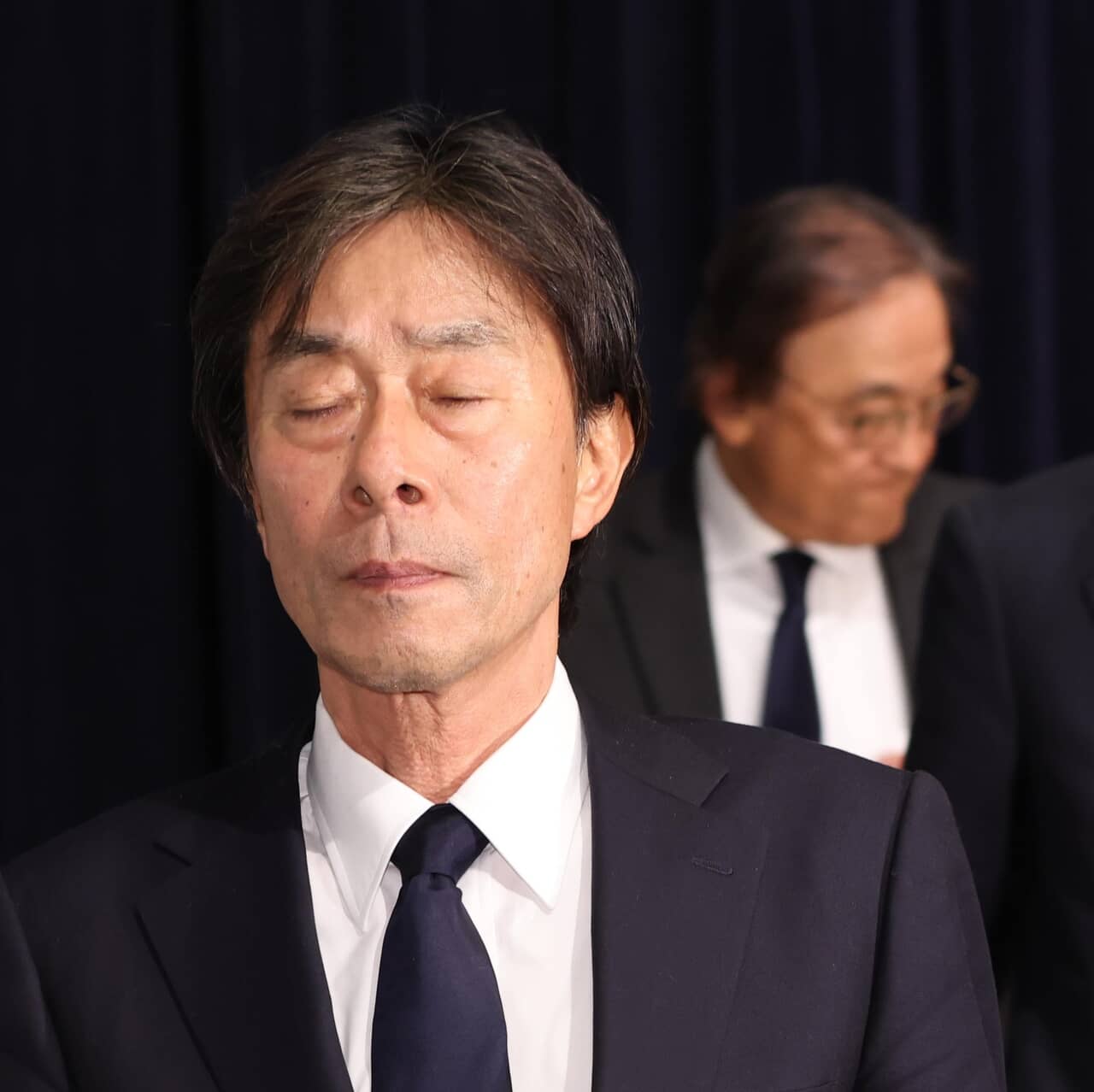なぜIT企業では人間が壊れるのか?「私は部品のように扱われている」IT支援現場で心を病んだベテラン社員の告白【谷口友妃】
なぜIT企業では人間が壊れるのか? #1
■正社員の話につられ…穏やかな日々が一変
しかし、ある日を境にSさんの穏やかな日常は一変する。
人事から、スキルアップの一環として外部プロジェクトへの参加を打診されたのだ。それは、通勤に片道1時間半かかる大手IT企業に常駐するヘルプデスク業務への異動の話だった。社員数1万人規模の超大手企業である。
環境の変化に不安はあったが、Sさんはこの話を受けることにした。
「かなり悩んだのですが、スキルアップの先に正社員への道もあるという話だったので、挑戦することにしたんです」
キャリアにつながると信じた先に、退職に追いこまれる未来があろうとは、想像もしていなかっただろう。
パソコンの調子が悪かったり壊れてしまったりしたお客さんの話を聞き、パソコンを修理する。パソコンの設定を行うキッティング作業や、お客さんのいるフロアで行う修理業務、インターネットの接続手続きなどにも対応した。
しかし、新しい環境で少しずつ違和感を覚えるようになる。
「発注元が作成した手順書に問題があることが多かったです。たとえば、手順書に記載されていない手順が実際には必要だったり、手順書通りに進めるとトラブルが発生したりといったことが頻発していました」
手順書とは、パソコン設定の流れが書かれたマニュアルのような書類だ。
IT技術者は手順書に書かれた通りにパソコンを操作して、会社で使えるように設定していく。
3年ほど前に作られた手順書は、改善点が反映されないまま使われており、手順書外のローカルルールも存在した。手順書が1種類だけであれば時間が解決したかもしれないが、作業ごとに複数の手順書が存在し、業務全体に曖昧な点があった。
当初、Sさんは手順書の不備を逐一報告していた。リーダーからの要請もあったからだ。しかし、リーダーからの返答は徐々に減り、1on1のミーティングもなくなっていった。課長との直接面談に切り替えて相談を続けたが、「もう少し様子を見てみましょう」との曖昧な回答に終始し、根本的な改善はされなかった。
これまでSさんが携わっていたプロジェクトでは、細かいルールを厳格に守ることでミスを防いでいた。しかし、新しいプロジェクトでは“曖昧さ”を前提として“臨機応変”な対応が求められた。頻繁に方針が変わる現場に、Sさんは戸惑った。
不備のある手順書で業務を続けると、パソコンの設定作業を最初からやり直すことになる危険性 もあった。
いつミスが起こるかわからない不安の中、複数の作業を同時進行することは大きなストレスだった。頼れるはずの管理者も頼りにならず、Sさんのプレッシャーは増すばかりだった。
やがてSさんは、通勤途中や勤務中に腹痛に襲われるようになってしまう。早めに出勤して食堂で休むなど工夫したが、体調は改善しなかった。
そして冒頭のように、不整脈で倒れる事態に至ったのだ。